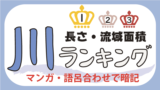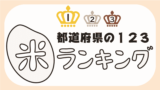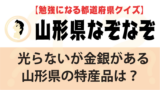山形県にむかしから伝わるご当地妖怪を日本地図とイラストで一覧表にして紹介します。
雪女(ゆきおんな)、つんぶく達磨(だるま)、ドロ田坊(どろたぼう)、鶴女房(つるにょうぼう)…。あなたの知っている妖怪もいるかもしれません。妖怪といっしょに都道府県の特徴や自慢などを紹介しているので、ぜひ覚えてくださいね。
山形県の妖怪・伝説
つんぶく達磨(だるま)
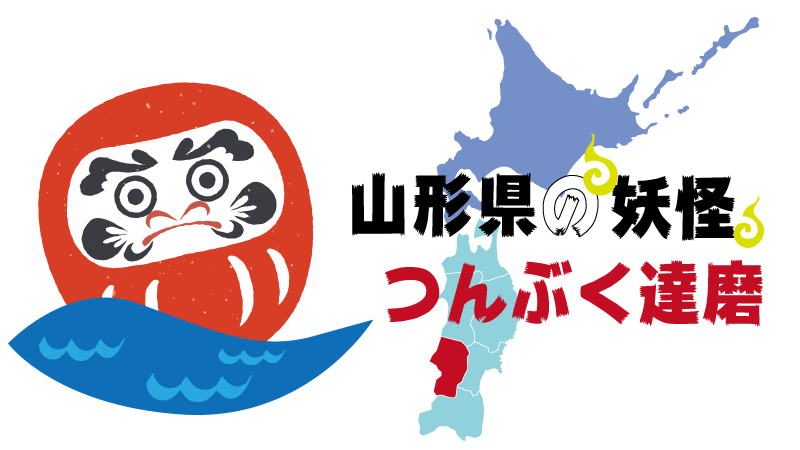
川を流れて病を治しにいく優しい達磨の伝説
「つんぶく達磨(だるま)」は、須川(すかわ)を流れ、やがて最上川(もがみがわ)を流れて村のはやり病を治したと言われる心優しい達磨の伝説です。
蔵王温泉(ざおうおんせん)から流れ出す須川のほとりに「おだるまの桜」と呼ばれる大きな桜がありました。桜のそばに寺があり、庭の小さなお堂に木のだるまがまつられてありました。村の子供たちはいつもだるま様と遊んでいましたが、ある日、須川に浮かべて遊んだまま忘れて帰ってしまいました。
だるま様は、つんぶくつんぶくと須川を下り、いつの間にか最上川の流れに乗って谷間を抜け盆地を抜け、最上峡を通り、広い庄内平野に出ました。さらに、つんぶくつんぶくと流され、とうとう酒田の浜辺につきました。
ちょうど近くを通りかかった村の名主様が拾って持ち帰り、ていねいに床の間にまつりました。だるまがやってきてから名主様の家では病人が出ないので、皆不思議がっていました。
あるとき、だるま様が名主様の夢に出てきて、『わしは最上川上流の「お達磨の桜」のそばにある寺のだるまです。村の人にはやり病が出て困っているので、もとの村に連れて行ってください』と言いました。名主様は、さっそく言われた村に返しに行きました。須川の村人は、だるま様が戻ってきたので大喜びです。はやり病もたちまちおさまったということです。
※山形県にある達磨寺に「つんぶく達磨像」があります。本堂にて常時公開されています。
ドロ田坊(どろたぼう)
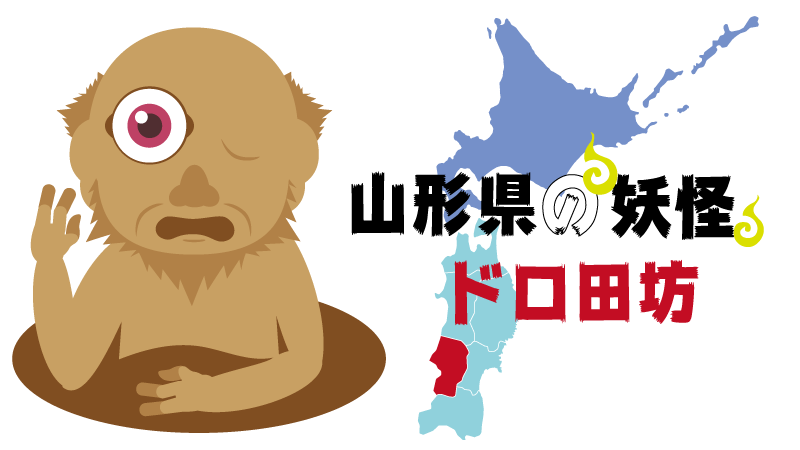
農作業をおろそかにする者をいましめる妖怪
「ドロ田坊(どろたぼう)」は、田んぼから上半身を出して「田を返せ」と、ののしる妖怪で全国の米どころに出現します。目が1つで色の黒い老人の姿だと伝えられています。
むかし、子どもたちのために一生懸命田を耕して米を作る翁(おきな)がいました。ところが、翁が死んでからというもの、子どもは酒を飲むばかりで田のことは一切しませんでした。さらに他人に田を売ってしまったのです。
それ以来、夜になると田から「田を返せ~田を返せ~」と泥田坊(どろたぼう)が現れるようになったと伝えられています。
雪女(ゆきおんな)
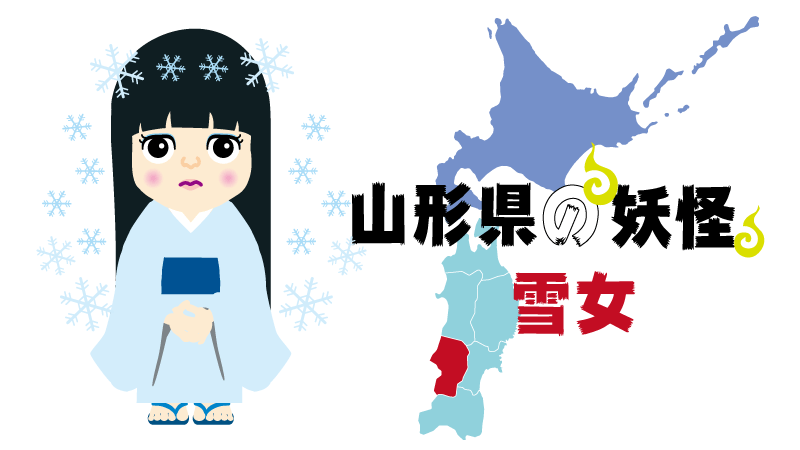
白い着物をまとい氷のように冷たい妖怪
「雪女(ゆきおんな)」は、吹雪(ふぶき)の夜にあらわれる雪の精霊(せいれい)です。着物は白く、肌も透き通るように白く、体は氷のように冷たいのが特徴です。雪女の伝承は全国に残されており内容はさまざまですが、雪女の正体がわかると雪煙(ゆきけむり)や雪となり、姿を消すと言われています。
山形県にも雪女の怖い伝承が残されています。
むかし、ある村に父親と息子の二人暮らしの家がありました。吹雪の晩のこと、二人が囲炉裏(いろり)のそばでうとうとと寝ていると、戸口から白い着物を着た肌の白い女が入って来ました。息子が気配を感じて目を覚ますと、女は父親の顔にフーッと息を吹きかけていました。父親はたちまち凍って死んでしまいました。
息子は恐ろしくなり寝たふりをしましたが、女はじろりと息子を見て「このことは誰にも言うな。話せば命を取るからな」と言うと、吹雪の中をスーッと出て行きました。息子は見たことを誰にも話しませんでした。
次の年の吹雪の晩、道に迷った女が泊めてほしいと訪ねてきました。囲炉裏のそばに寄らず、温かい汁も飲まない女を不思議に思いましたが、話すうちに気心が知れ二人は夫婦になりました。そのうちに赤ん坊も生まれ、幸せに暮らしていました。
子どもが3つか4つになったころ、また吹雪の夜がやってきました。息子は「お父さんの死んだ夜もこんな吹雪の夜だったなあ…」とポロリと言ってしまいました。
すると女は恐ろしい声で「言ってしまったな!約束を破ったから、もうここにはいられない」と言い、長い髪をふり乱して外に飛んでいき、もう二度と戻ってはきませんでした。
鶴女房(つるにょうぼう)
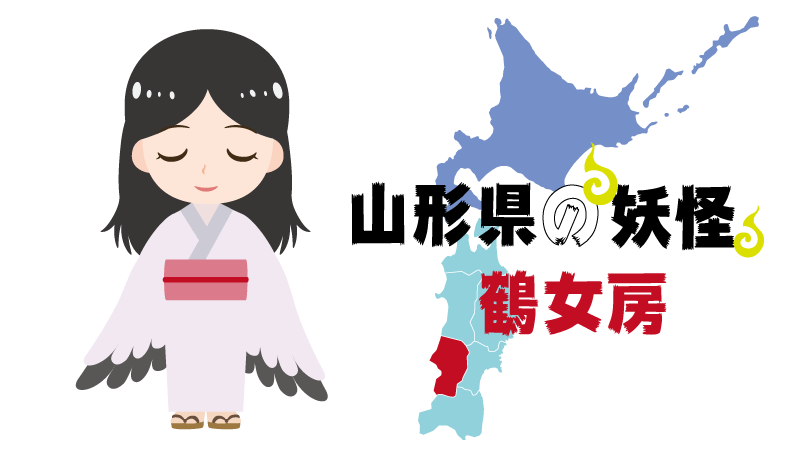
絵本『鶴の恩返し』に登場
「鶴女房(つるにょうぼう)」は、絵本などにある『鶴の恩返し(つるのおんがえし)』に登場する、鶴の妖怪です。山形県南陽市に伝わる鶴の恩返し伝説は、江戸時代の書物に残されています。
むかし、いじめられていた鶴を助けてやった男がいました。夜、男の家に美しい女がたずねてきて、「妻にしてほしい、働かせてほしい」と何度も男に頼むので、仕方なく女を迎え入れました。その女は織物(おりもの)が上手で、織った布はとても高く売れましたが、布を織っている間は「部屋をのぞいてはいけない」約束でした。
しかし、男は窓のすき間から部屋をのぞいてしまいました。そこにはやせおとろえた一羽の鶴が自分の羽毛(うもう)で布を織っていたのです。男は驚いて声を出してしまい、男に助けられた鶴だと正体がばれた女は織り上げた「おまんだら」を男に渡して消えました。
その後、男はお坊さんになったそうです。
山形県には鶴の毛織物が寺の宝にされていたと伝えられる「鶴布山珍蔵寺」があり、寺の釣鐘(つりがね)には鶴の恩返し伝説が描かれています。
佐藤七右衛門『池黒村付近の伝説私考』より
※妖怪の話はこちらに掲載されている内容と異なるものもあります。
※同じ妖怪・似た話がほかの都道府県にも伝わっている場合があります。
※妖怪のイラストはイメージです。